油壺の種類 | 油絵で使う油壺の使い方と特徴
このページの目次
油壺とは
油壺は、絵具に混ぜる画用液を入れておく容器です。油壺にあらかじめ付いているクリップを使って、パレットに固定します。
油壺の特徴と種類
油壺の素材や形状は製品によってそれぞれ違い、使いやすい相性の良いものを選べると良いでしょう。
油壺の素材は、アルミやステンレス、真鍮の金属製のものが主流です。陶器製のものもありますがパレットに固定することはできません。安いものだとプラスチックや樹脂製の製品もありますが、おススメしません。
油壺は壺の数が1つ口の製品と2つ口の製品があり、密閉できる蓋が必ず付いています。そして陶器製のもの以外はパレットに固定できるクリップがついています。
油壺の口径は、2.5cmから3.5cmほどで、陶器製のものだと6cmぐらいあります。
油壺の形状は、ソロバン型、筒形、平底型などがあり、以下がそれぞれの特性です。
- ソロバン型
- 画用液がこぼれにくく、少量の量の画溶液を入れても使いやすい構造です。
- 平底型
- こぼれにくく、ソロバン型に比べて多くの量の画用液を入れることができます。
- 筒形
- 大きめの筆を使用する際に適していて清掃しやすい形状です。
油壺の使い方
一般的に油壺は画用液を入れて、パレットに油壺のクリップで固定して使用します。パレットに固定する利点は、パレットに出している油絵の具と画用液をすぐに混ぜることができる点です。
油壺に入れる画用液は主に、揮発性油と乾性油になります。速乾性の画用液は清掃するのが困難なので油壺に入れるのは、おススメできません。
油壺に入れる画溶液を多く入れてしまうと、こぼれる原因にもなりますので、半分ぐらいまでにとどめておくのが無難です。
通常、描きはじめは揮発性油を使用することが多いので、油壺には揮発性油を入れておきますが、制作が進むにしたがって、乾性油の量を増やして調合するようにしていきます。
2つ口に油壺の場合は、あらかじめ揮発性油と乾性油を分けることができるし、自分なりに調合した2種類の画用液を用意することが可能です。通常、1つ口の油壺で作業に支障はありません。
油絵の具に画用液を混ぜる場合は、パレットの空いたところに絵の具を用意し、油壺の中が汚れないように絵筆を画用液に浸してから、適量の画用液を絵の具に混ぜます。このときムラがないように絵の具に画溶液をしっかり混ぜ合わせる必要があります。
油壺には蓋があるので画用液を使用しないときには、しっかり密閉しておきます。しかし密閉しておいた画溶液で長期間使用しなかったり、品質に変化がある場合は廃棄しましょう。油壺を長持ちさせるために、不要な画用液を廃棄した後は、筆洗油などの揮発性油で清掃しましょう。
オリジナルの油壺を用意する
油壺は、パレットを手に持って使用する場合、非常に使い勝手が良いですが、大量の画溶液を使用する場合などには適していません。
また、油壺に絵筆が入らない場合もあるし、ペインティングナイフで描くときなどは、あまり使いやすいとはいえません。
そんな時は、日本画などで使うような陶器製の白い"溶き皿"が便利です。美大の受験生や美大生などの多くも"溶き皿"を利用しています。
"溶き皿"は大量の画溶液を扱うことができるし、刷毛などにも対応する口径があるので使いやすいと思います。
また、ガラス製の蓋がついている口径の大きな空き瓶を見つけてきて、油壺の代わりにすることもできます。中には筆洗器を油壺代わりに使用しているツワモノもいます。
油壺-おススメ画材
筒型 油壺
ホルベイン 油壷 筒型 No.14
- 大きさ:口径33.5φ×外径37.5φ×厚さ45(mm)
- 形状:筒型
- 材質:スチール製
スチール製筒型。ソロバン玉型に比べて口が広いので、大きいサイズの筆も使用できます。また、使用中の画溶液の汚れが分かりやすく、掃除もしやすいシンプルな形です。
陶器製卓上型 油壺
ホルベイン 磁製(セラミック)油壷
- 大きさ:口径60φ×外径(84φ×2)×厚さ45mm
- 形状:大口径の筒型2ヶ1組
- 材質:セラミック製
- その他:木製トレイ付
溶き皿
SEIWA 染色容器類 溶き皿 大
- 大きさ:直径11cm
- 12枚入り
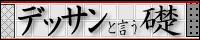



![溶き皿 11cm 12枚[SEIWA]](https://m.media-amazon.com/images/I/51RsH1O0QRL._AC_SL160_.jpg)
