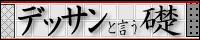キャンバスの種類と使い方 | 油絵で使うキャンバス
このページの目次
キャンバスとは
キャンバスは油絵の支持体です。支持体とは、描いて表現される絵画を支える物体のことです。油絵の支持体は主に、板、紙、キャンバスなどがあります。
油絵で最も需要があり、使用される頻度が多いのがキャンバスです。キャンバスは布地に下地を施したものを木枠に釘などで固定して使います。
下地を施したキャンバスを木枠に張っている製品は"張りキャンバス"といいます。別々に木枠とキャンバスを選んで自分で張ることもできます。
木枠に張られていないキャンバスは、木枠の大きさに合わせてカットされたものと任意の大きさにカットできるロールキャンバスが売られています。それらには、下地処理に違いがあるため、下地の施工状態を確かめて購入する必要があります。
アクリル絵の具を併用する場合はアクリル絵具と油絵具の両方を使用できる下地のキャンバスを選びます。ただ、そのような下地でも油絵具の上にアクリル絵具を描写することはできず、アクリル絵具は油絵具の下層に描かれていなければなりません。
キャンバスの特徴
他の支持体と比べ、キャンバスは軽く丈夫で、丸めて保存ができます。市販されている張りキャンバスは釘によってキャンバスが木枠に固定されています。
描かれたキャンバスは、釘を抜いて取り外すことができ、描かれている表面を外側にして、丸めて保存することができます。内側にして丸めると剥離する原因になります。残された木枠は、キャンバスを自分で張って再利用できます。
キャンバスを張るには、専用の道具をいくつか用意する必要があり、張り方にもコツがあります。キャンバスの張り方を参照してください。
キャンバスの種類
キャンバスを選ぶときは大きさ以外に、布地、布目、下地の性質を考慮します。下記はそれぞれの種類と特徴です。
キャンバスの布地
- 亜麻・麻
-
非常に繊細で伸縮が少なく、油の酸化などに強い素材です。また、織り糸がしっかりしていて、下地塗料の定着が良く、丈夫で強度があり、大きな作品に向いています。細密描写や厚塗りなど目的に応じて適応できる布地です。油絵に適している素材で一番需要があります。
「亜麻」は亜麻科のフラックスが原料であるリネンのことです。「麻」は植物から作られる繊維の総称のことを指し、「亜麻」も含まれます。 - 綿
- 亜麻・麻に比べ繊細な綿は、滑らかな画面をつくり、細密描写に適しています。しかし、油の酸化に弱く、厚塗りには不向きです。また、織り糸が動きやすくて、乾燥により裂けやすくなり、湿気により伸縮しやすい特徴があります。大きな画面の使用にあまり適していないので、使用する際は板に張り付けたり、下地の強度を強したりする必要があります。亜麻・麻よりも安く入手することができます。
- ナイロン
- ナイロン製の画布は害虫や湿気に強く、湿気による伸縮が少ない特徴があります。アクリル画、水彩画、日本画に適した画布です。
キャンバスの布目
布地にはいくつかありますが、布地の織り方は平織という方法で織られています。織られる糸の太さや糸の数によって織り目の状態が変わり強度にも差が出てきます。また、布目の状態で描かれる絵の表情にも影響を与えます。
- 荒目
- 織り目が大きいのが荒目です。強度が強いので大きな作品に適していて、光を乱反射する傾向があるため、艶消しのマットな印象を与えます。目が荒いので細密描写には不向きです。
- 中目
- 荒目と細目の中間の織り目です。一般的に一番好まれていて、良く使用されるのが中目です。
- 細目
- もっとも、織り目が滑らかで、細密描写に適しています。荒目と比べて強度が弱く、大きな作品には適しているとはいえません。平滑なため、光を正反射する傾向があるので、光沢のある印象を与えます。
キャンバスの下地
どのような布でも油絵を描くためには下地処理を施すことが必要です。通常、販売されている張りキャンバスには下地処理が施されているので、すぐに描くことができます。キャンバスのみで販売されている物では、下地処理されていないものもあるので注意しましょう。
下地処理されることで布の酸化を防止し、布地の織り目を固定させ強固にさせる作用があります。そして、油絵の固着を良くし、白い下地は発色を良くします。
下地処理の方法は、まず、布地を保護するため、膠やカゼイン、PVA(ポリビニールアルコール=ポバール)などによる目止め処理が行われます。この膠層を前膠やサイズ(size)といいます。目止めの後に、描画する画材や描く方法に合った地塗り(下地)の材料が塗布されます。
下記は目止めを行った後の下地の種類と材料、特徴です。下地の吸収性などの性質によって、描写できる絵具の種類が限定されます。
| 下地の種類 | 材料 | 特徴 |
| 油性下地 セリューズ地 【非吸収性】 |
白色顔料(鉛白)+乾性油(リンシードオイル) | 油絵具のみに使用できる下地で、乾性油にリンシードオイルが使われているため、黄色みがかっています。油性地は絵具の油分をあまり吸い込まない非吸収性で、油絵具特有の艶を引き出し、絵具の乾燥は遅いです。 |
| 水性下地 【吸収性】 |
白色顔料(白亜=炭酸カルシウム、あるいは石膏)+膠水 | 吸収性が高く吸着が良いので、油絵具やアクリル絵具、テンペラに使用できます。吸収性なため艶のない画面になりやすく、厚塗りは亀裂の原因になります。顔料に白亜(炭酸カルシウム)を使用したものが白亜地、石膏を使用したものが石膏地と呼ばれます。 |
| エマルジョン地 【半吸収性】 |
白色顔料(白亜=炭酸カルシウム)+エマルジョン | 水性と油性の中間の性質がある下地です。半吸収性ですが油分を増量させることで非吸収性に近づきます。油絵に適していて、吸収性が良いほど、アクリル絵具やテンペラも併用できます。 エマルジョンとは、膠水に乾性油(リンシードオイル)を分散乳化させた乳濁液です。 |
| アクリルエマルジョン地 【半吸収性と同様の性質】 |
白色顔料+アクリルエマルジョン | 市販されている多くのキャンバスに使用されている下地です。油絵具やアクリル絵具、テンペラに利用できます。 |
制作の目的別のキャンバスの使い方
使用するキャンバスは、描き方に特別な目的や狙いがない場合、亜麻でできている中目の油絵用のものを使用すると良いでしょう。その場合、一般的に市販されている"張りキャンバス"が、手間がかからずに手にしやすいです。
安価なものは下地の成分が表示されていないことがあります。アクリルとの併用ができるキャンバスは、アクリルエマルジョンが下地処理されている物がほとんどです。
油絵の制作に慣れてくると、キャンバスの性質にこだわりが生まれるかもしれません。そんな時は、好みのキャンバスを選んだり、自分で下地を塗ったりすることになります。
下記は、描き方別にキャンバスを選ぶヒントです。
- 細密描写
- 亜麻でできた細目のキャンバスは平滑な画面なので細密描写に適しています。小さなサイズの作品なら綿のキャンバスを選んでもよいでしょう。また、中目のキャンバスでも、その上から再度下地処理を施して、目を埋めて滑らかな画面をつくれば、細密描写ができます。
- 厚塗り描写
- 亜麻でできた荒目のキャンバスが丈夫にできていて厚塗りに適しています。画面全体でなく、部分部分の厚塗りでしたら、中目でも大丈夫でしょう。
- 大型の作品
- 亜麻でできた荒目のキャンバスが丈夫にできていて大きな作品に適しています。大型のキャンバスに細密描写する場合は、目を埋めて細密描写に適した平滑な画面に下地処理すると良いでしょう。
- アクリル絵具との併用
- アクリル絵具を使用する場合は、アクリル絵具の使用に耐えられるキャンバスを使用しましょう。水性で吸収性の下地なら、アクリル絵具の使用はできると思います。現在、多く流通しているアクリルエマルジョンの下地を施したものが一番手に入れやすく、安心してアクリル絵具を使用できます。アクリル絵具は油絵具の上に描くと剥離するので、アクリル絵具は最初に使用しなければなりません。アクリル絵具の上から油絵具を描くことは問題ないとされています。