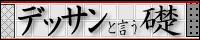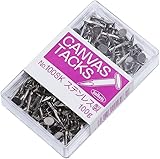キャンバスの張り方と張る道具 | 油絵で使うキャンバス
キャンバスを自分で張る利点
張りキャンバスではなく、キャンバスだけを購入して、木枠に張ることはお金をかけずに済むのでおススメです。
このとき木枠のサイズに切られているキャンバスをカットキャンバスと呼びます。そして、自分で任意の大きさに切るためにロール状で販売されている大きな面積のキャンバスをロールキャンバスと呼びます。
木枠を流用する
油絵を始めるとき、多くの人は市販されている"張りキャンバス"を購入して描き始めます。
このキャンバスに描いた絵画が乾いたら木枠からはがして、木枠を再利用することができます。キャンバスだけを買って、木枠に自分で張ることができれば出費を抑えることにつながります。
キャンバスを張るために必要な道具
キャンバスを張る環境
キャンバスを張るにはコツがあります。張る作業の手順や方法をしっかり把握しておく必要がありますが、キャンバスを木枠に張った出来具合は、湿度や温度などの環境に大きく左右します。
キャンバスと湿度
一般的にキャンバスは、湿気によって伸びる性質があります。その性質を利用して、湿度が高い日にキャンバスを張ることが良いとされています。乾燥した日にキャンバスを張ると、湿度の高い日にキャンバスが弛む可能性があります。
ただ、多くの水分をキャンバスに与えた場合、逆にキャンバス地が収縮する性質があるので、水分を与えればキャンバス地が伸びると安易に考えない方が良いでしょう。
張りキャンバスの弛んだ個所の裏側に霧吹きで水分を与えるとキャンバスが強く張りますが、それが水分でキャンバス地が収縮する性質を活かした例です。
適度な湿度があるとキャンバス地が伸びるのは間違いがないようですが、その度合いはキャンバスの素材によって違うようです。
キャンバスを張るのに湿度が関係していますが、あまり神経質になる必要はないと思います。しっかりキャンバスを引っ張って張りさえすれば、簡単に弛むことはないでしょう。
キャンバスの保管と温度
湿気などの水分の他に、温度がキャンバス地の伸縮に関係している疑いがあります。
熱で伸びたという事象があり、それには目止めに使用されるPVA(ポリビニールアルコール=ポバール)などの水性樹脂糊が関係しているのではないかという疑念です。
PVAは耐熱性なため、簡単に伸びるとは考えにくいです。ただ、車内や密室などの高温になる場所に置いていた張りキャンバスが弛むことがあるようです。弛んだ場合、元に戻ることはないようです。
以上のことから、張られたキャンバスは風通しが良く、高温多湿でない暗い場所で保管すると良いでしょう。
キャンバスを張る方法
- 木枠を組み立てます。木枠の方向と位置を確かめながら、手で組み込んで組み立てます。その際、結合部分がしっかり結合されるように、木槌とあて木を使って組み立てます。
- 組み立てられた木枠に歪みがないか確かめるために、平地に置き歪みのないことを確かめ、木枠の結合部分が直角になっているか三角定規をあてて確かめます。
- キャンバスを用意します。張りたいキャンバスの大きさよりも縦横木枠の厚み+4cm程大きくしたキャンバスが必要です。その理由は木枠に巻き込んで釘で打ち付ける部分が必要だからです。
- 用意したキャンバスを作業台などに裏返して広げます。その上に木枠をのせます。木枠からはみ出すキャンバスが均等な距離になるように配置します。木枠にも表裏があるので表を下にします。キャンバスに接地する木枠の表側は、木枠が傾斜していて、角が取れて丸みがあり、キャンバスにあたる面が少なくなっています。
- キャンバスに木枠をのせたら、木枠に沿って、キャンバスに織り目を入れて、配置する目安をつけておきます。
- 木枠にキャンバスを釘で打ち付けていきます。まず、長い方を横にして、中央に釘を打ち込みます。
- 次に反対側に釘を打ち込みます。反対側は、キャンバス張り器でキャンバスをはさみ、木枠にあてて、てこの原理で引っ張りながら、釘を打ち込みます。引っ張る力が強すぎるとキャンバスが裂けるので注意しましょう。
- 2か所固定されてから、短い方を横にして、キャンバス張り器で引っ張りながら、釘を打ち込みます。そして、反対側の中央も釘で固定します。
- その後は、中央から外(角)に向かってバランスよくキャンバス張り器で引っ張りながら、等間隔で、キャンバスを釘で固定します。
- 最終的に四隅に到達すると、キャンバスが余りますが、それらは折りたたんで、キャンバス張り器で引っ張りながら、釘で固定します。
- 以上が、キャンバスを張る作業の流れです。うまく張られていれば、キャンバスの中央部を指ではじいたら、パンパンという気持ちいい音がします。弛んでいたら、部分部分で釘を打ちなおすと良いでしょう。
大きなサイズを張るときは釘を何か所か仮止めしておきます。ある程度固定した後に、仮止めした釘を抜きながら、改めて釘を打って固定すると作業が進みます。