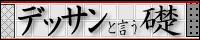初心者が覚えたい画用液の使い方 | 油絵で使う画用液
このページの目次
初心者が覚えるべき画用液
油絵具はそのまま描けるものの、正直言って描きづらいです。そのため、"水彩画のようにサラサラ描けたら良いのに"と思うのではないでしょうか。
水彩画のようなタッチを生むものに揮発性油があります。キャンバスに描き始める下描き段階では揮発性油を多めに使用しながら描くことで、キャンバスに絵具が浸透します。
揮発性油で薄く描くことで構図や配色などの絵画の構想を練ることができます。描いた箇所を布に含ませた揮発性油で拭い取ることも可能です。
揮発性油は文字通り、揮発する成分で固着力がありません。油絵具に練られている乾性油には固着力がありますが、揮発性油を混ぜることでその力が失われてしまいます。
"それなら乾性油だけで描けばいいや"と思う方もいるでしょうが、乾性油は揮発せず、酸素と反応して固まるため、使用した分だけ油が固まります。
乾性油の量が増えた分、絵具の顔料の密度もなくなり、鮮やかさは失われます。その油分が固まりだすと光沢ともいえないテカテカの画面になります。更にその上には油絵具が浸透しづらく加筆しづらいため、その上から描くことも困難になります。
そこで、絵具の浸透も促し、固着力や皮膜力を強くするために、揮発性油と乾性油を調合した油が必要になります。基本的な使用方法は、揮発性油で描き初め、徐々に乾性油の割合を多くさせていきます。揮発性油と乾性油を混ぜる配合比率はさまざまで、配合比率次第で画肌が違ってきます。
初心者はまず、揮発性油と乾性油の特性や使い方を覚えておくといいと思います。後々さまざまな応用が利くようになります。
揮発性油の選び方
揮発性油はさまざまな場面で使用しますので特性を理解しておくと良いと思います。下記にまとめてみました。
揮発性油の特性
- 油は揮発する。
- 油はサラサラしている。
- 絵具の流動性を増す。
- 絵具の乾燥を早める。
- 絵具の艶を失わせる。
- 皮膜形成力がない。
- 絵具に含まれる乾性油を溶かし定着力を弱くする。
- キャンバスと下地へ浸透しやすく、油絵具の定着を促進させるための素地をつくるので、描きはじめに多く使用する。
- 下描き(描きはじめ)以外は乾性油や調合油と使用する。
- 中描き~仕上げの使い過ぎは剥離の原因になる。
一般的に使用される揮発性油は、テレピン(ターペンタイン)とぺトロールです。通常1つあれば大丈夫です。テレピンとぺトロールには上記の特性があり、それぞれ違う性質もあるので下記にまとめました。
テレピン(ターペンタイン)の特性
- 松ヤニを蒸留、精製した揮発性油。
- 揮発性油の中で最も揮発度が高いので乾燥が早い。
- 長時間空気に接すると酸化重合して黄変し、粘度が増す。樹脂化する場合がある。
- 樹脂を溶解するのにすぐれている。
ぺトロールの特性
- 石油を精製した揮発性油。
- テレピンに比べ揮発度が低いので乾燥が遅い。
- 完全に揮発し樹脂化することはない。
- 揮発する際に乾性油の一部も損なう。
- テレピンに比べ溶解力は弱い。
- 一部のワニスを白濁させる性質がある。
- 筆洗液として使用できる。
- 画面保護ワニスの除去に使われる。
上記を読むと樹脂の溶解力の強さや、樹脂の溶剤として使うことを考るとテレピンがおすすめです。密閉して保管すれば簡単に黄変することはないと思います。ただ、ぺトロールは画用液以外にも使用方法があるので重宝しそうです。
乾性油の選び方
乾性油はさまざまな場面で使用しますので特性を理解しておくと良いと思います。下記にまとめてみました。
乾性油の特性
- 油は酸素と反応(酸化重合)して固まる。
- 絵具を画面にしっかり定着する。
- 絵具は顔料に乾性油で練られてつくられる。
- 絵具に粘りを与える。
- 絵具の乾燥が遅れる。
- 絵具に透明度と光沢を与える。
- 滑らかな画面をつくる。
- 使い過ぎると油分が目立ち、加筆できなくなる。
- 主に中描き~仕上げで使用する。
一般的に使用される乾性油は、リンシードとポピーです。どちらか1つあれば大丈夫です。リンシードとポピーには上記の特性があり、それぞれ違う性質があるので下記にまとめました。
リンシードの特性
- 亜麻仁油。亜麻の種子から搾り取られた油を精製。
- ポピーと比べて乾燥が早く、堅牢である。
- 黄変しやすいので白や淡色には不向きである。
- 暗所で黄変が進み、光に当たると漂白する性質がある。
ポピーの特性
- 芥子(ケシ)油。ケシの種子から搾り取られた油を精製。
- リンシードと比べて乾燥が遅く、堅牢さに劣る。
- 黄変しないので白や淡色に向いている。
- 使い過ぎは亀裂の原因になる。
上記を読むと画用液には乾燥の速さと堅牢さからリンシードがおすすめです。ただ、上描きに使う白や淡色の描写は黄変しないポピーを使用するのも良いかもしれません。
基本的な画用液の調合方法
油絵を描く順序はキャンバスに下描き(描きはじめ)、中描き、上描き、仕上げ、といった段階で描かれていきます。下描き、中描き、上描き、仕上げの段階ごとに揮発性油より乾性油の比率を上げて描いていかなければなりません。
基本的な混合比率は揮発性油50%、乾性油50%と覚えておきましょう。
調合は油壺に直接入れても良いですが、あらかじめ調合用にビンを用意して、その中で調合しても良いでしょう。
揮発性油と乾性油の使い方の例
- 下描きでは、揮発性油を使います。揮発性油だけで使えるのはこの段階だけです。
【混合比率】揮発性油100%:乾性油0% - 中描きの段階では、固着力と皮膜を強くするために乾性油を加えていきます。段階的に乾性油を増やすのは、絵具の浸透性を維持し加筆を促すためで、中描きの段階では控えめにしたいです。
【混合比率】揮発性油50~70%:乾性油30~50% - 上描きの段階で完成に近づくため、透明度と光沢を考慮して、最終的な画肌に近づけるように乾性油を増やして調整します。
【混合比率】揮発性油30~50%:乾性油50~70% - 仕上げの段階では、画面全体の透明度と光沢なども考慮しながら油を調整し、修正加筆を繰り返します。
【混合比率】揮発性油20~50%:乾性油50~80%
画用液の使い方の発展
中描きの段階から、画用液の10%程度の乾燥促進剤(シッカチーフ)を加えることで乾燥を促進させることができます。他にも描画用ワニス(ダンマルワニス)などを画用液の10~20%ほど加えることで乾燥を促進し、透明度や光沢を調整します。
ダンマルワニスは画面の透明度や光沢に影響するので、乾性油とダンマルワニスの混合比率を調整します。あらかじめ調整されたパンドルを使用するのも一つの方法です。中描き~仕上げの段階で使用すると良いと思います。
描画用ワニスは乾燥が早く便利ですが、画用液などに加えながら適度に使用しましょう。
画用液を扱う上での注意
調合した画用液を保管するときはビンを利用しましょう。プラスチック容器などでは、画用液の成分に変化をきたしたり、容器が破損する恐れがあります。
乾燥促進剤の使用は、発火の恐れがあるため、注意が必要です。乾燥促進剤のシッカチーフなどは発火温度が低く、シッカチーフがついた布や紙が自然発火する恐れがあります。その場合、焼却するか、多くの水に含ませて廃棄しましょう。