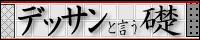光源の性質と効果
光源の性質と効果は千差万別です。デッサンや絵画作品を描くうえで必要な光源の性質と効果を理解しましょう。
光源の主な種類と特徴
光源には主に下記の表にある自然光と人工光があります。
┌自然光……………………太陽光(月光) │ │ 光源─┤ ┌温度放射……白熱ランプ │ │ │ ├放電…………蛍光ランプ └人工光─┤ ├有機EL、EL…発光ダイオード(LED) │ └燃焼…………焚火、蝋燭、石油ランプ
- 太陽光
- 一般的に自然光である太陽光の下、見ることができる色が自然な色で固有色です。さまざまな照明も太陽光の性質と比較することで自然な色を演出することができます。逆に自然光の分光分布が変化した照明を利用すれば、特殊な演出が可能になります。
- 月
- 自然光である月光は、厳密にいえば太陽光が月で反射した光です。
- 白熱灯
- 点光源に近い暖色系の光で演色性能が高いです。光沢を増して、反射が多く、明暗のコントラストをはっきりさせ立体感が出やすい光です。
- 蛍光灯
- 寒色系の白色の光で空間全体を均一に明るく照らします。拡散光であるため光源が遠ざかるほどぼやけて、明暗のコントラストは弱いです。昼光色(D)6500Kや昼白色(N)5000Kなど色温度別に商品が用意されています。昼光色6500Kは太陽光6000Kに近い光ですが、多少青っぽい光なので、昼光色よりも暖かみのある昼白色が好まれる場合もあります。※色温度Kは次の項目参照
- 発光ダイオード(LED)
- 点光源に近い光で、光沢を増して、立体感が出やすいです。熱線や紫外線がほとんど含まれていません。
色温度(K)とは
色温度(いろおんど)は、ある測定方法により光源の光の持つ色を数値化したものです。単位をK(ケルビン)で表示します。色温度が高いほど青色へ近づき、色温度が低いほど赤色へ近づきます。難しいことはさておき、電球や電灯の色温度はそれぞれ違うので、色温度の表示で光の特性を判断し、必要な光源を求めることができます。
色温度の例
- 日中の太陽光:5000K~6000K
- 朝日、夕日:2000K~2500K
- ろうそくの光:1800K
- 色彩工学の標準光:6500K
電球の色温度の例
- 一般白熱電球100W:2800K
- 電球色蛍光灯(L色):3000K
- 温白色蛍光灯(WW色):3500K
- 白色蛍光灯(W色):4200K
- 昼白色蛍光灯(N色):5000K
- 昼光色蛍光灯(D色):6500K
光源の性質と利用
私たちは光源から発せられる光によって物を見ることができます。当然のことですが、光源がなければ世の中は暗闇になり、多くのものは死んでしまうでしょう。
光源の種類によって、あらゆるものの価値は変化し、意味が変化する場合があります。光源が同じでも、その光は私たちに届くまでに、昨日とは違った性質のものになることがあります。
商業施設では、多くの人工光の照明が使われ、その種類や性質は用途によってさまざまに違います。
食べ物をおいしく見せるためのディスプレイと照明、洋服をよりよく見せるためのコーディネートと照明など、商品を売る施設では目的意識を持った照明方法が施されています。
その照明方法はコストも考慮しなければなりませんが、常に光源と商品と消費者の関係を考えながらコントロールされています。
その反面、自然光である太陽光では、すべてをコントロールすることは難しいといえます。
室内に太陽光を取り入れる場合、光を遮ることは容易ですが、光を今ある以上に多く取り入れることは簡単にはできません。それは季節によって違い、大気の状態からも日々同じ状態のものはないといえます。
そのため人工光を採り入れて光を補うことになります。しかし、自然光と人工光の光源の場所が違うことは光の方向が違うため映し出される物の表情が変化していきます。
デッサンや絵画では光源からの光を利用して描いているので、その光を発する光源の性質を理解して、光源とモチーフと観察者(自分)の関係を良好に保つようにしましょう。
デッサンや絵画における光源
光源の場所よって光の方向や強さが違うので、描く対象のコントラストや色彩、雰囲気が違ってきます。
光源によって光が変化する場合、デッサンや絵画制作では、描きたい衝動に至った対象をしっかり心に刻む努力をしなければなりません。
特に、風景などの野外制作などでは描きたいと思った場面は褪せやすいものです。
クロード・モネが描いた『ルーアン大聖堂』
ルーアン大聖堂 扉口 1893 
ルーアン大聖堂 扉口、太陽 1892-1893

ルーアン大聖堂 1892-1893

屋外での写生などは刻一刻と表情を変えるため、早く描く技術が要求されます。
印象派のクロード・モネが描いた『ルーアン大聖堂』では、朝、昼、夕と別にキャンバスを分けて描き分けています。時間ごとに変化する光がうつし出す大聖堂のコントラストや陰影、色彩,雰囲気はそれぞれ違う絵画として観るものを魅了します。
現代ではアントニオ・ロペス氏のように季節や時間にこだわり、同じ場所で同じ光を求めて制作する作家がいます。
その反面、スケッチの代わりに映像や写真を代用する現代作家が多くなってきています。それは、手早く対象の色や雰囲気を切り取ることができるからだといえます。あるいは、対象にある絵画の要素のとらえ方の違いが、現場にこだわらない理由の要因にあると考えられます。
室内で制作する写実絵画では、光源を自分独自のものにするため、蛍光灯を何本も並べられる照明器具を制作し、一方向から安定した光があたるように工夫する作家もいます。野田弘志氏は、そのような制作をしていたと思います。