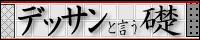具象画と抽象画の両方に対応できる描写力を育む
具象画と抽象画の両方に対応できる描写力、描き方を育む方法について紹介します。この方法・ガイドラインによって絵画を描くための総合的な能力を高めることができます。

さまざまな絵画を理解し描くための2つの側面
具象画や抽象画にこだわらず、さまざまな絵を描く能力を高めるためには、大きく2つの側面を成長させる必要があります。
一つは絵を描く技術で、もう一つが感性です。
この2つの側面を成長させることで、絵を描く能力が高まります。
『なんだ、そんなの当たり前だろ』と思われる方も多くいると思いますが、多くの人は意外と感性を成長させることをなおざりにしがちになります。
この技術と感性の2つの側面をバランスよく育むことができれば、具象絵画と抽象絵画の両方をしっかり理解し描くことができるようになります。
参考ページ
具象絵画と抽象絵画を理解できるようにする
技術と感性をバランスよく成長させることで具象絵画と抽象絵画にとらわれることなく描く能力を高めることができ、それとともに具象絵画と抽象絵画の両方をしっかり理解できるようになります。
この点は特に重要で『写実的絵画が一番優れている』または『抽象絵画がもっとも重要である』など、一方のジャンルにとらわれているような意見を冷静に受け止められるようになります。
絵画をジャンル分けして、どちらかを見下してみるような作家が、意外と多くいるので注意したいところです。
参考ページ
絵を描く能力と年齢
絵画作品を制作するためには、日常のものごとや時代のトレンドなどをイメージすることができる感性と、そのイメージを具現化することができる技術が必要です。
これは年齢がいくつであっても、この2つの側面は絵を描くためのガイドラインとして意識する必要があります。
おおむね幼少期は感性が充実していますが、技術力はありません。その後、成人になるにつれて感性は貧弱になり、技術力は高まります。
例えば幼少期であれば、クレヨンの握り方くらいを教えておけば、素直に感じた色や形を殴りがきするように描いていきます。
幼少期は感性が強いので、多くの技術を教えなくても、さまざまな技術を編み出して自由に自分の感じたことを絵画として表現します。
それらの絵画は、大人にはまねできない自由で豊かな色と形が折り重なって鑑賞者を魅了します。
やがて中学生や高校生くらいになり絵を描く技術が身につくと、客観的で写実的な絵画が描けるようになります。
このとき、技術力が身につくのと反比例するように、作者のなかにある感性が減退しているように感じられる場合があります。
それは主観的な見方が悪いものかのようにそぎ落とされて、だれが見ても納得のできる客観的な見方へ作品が収束されていくように感じられます。
そのような絵画からは写実絵画を描くための技術力に魅了されますが、作者独自の感性を見つけることが難しくなります。
参考ページ
絵を描く技術を高める方法
技術的な面は学校教育や書籍、動画などでいくらでも学ぶことができると思います。
特に学ぶべき技術はルネサンス以降に研究されてきた写実的絵画や具象絵画にあります。
そしてルネサンス以降は後期印象派の平面化される絵画の変遷まで少なくとも理解しておく必要があります。
それらの技術、技法は具象絵画だけでなく抽象絵画にも応用できる技術なので、しっかり理解しなければなりません。
効率よく絵画の技術、技法を学ぶために絵画教室を利用することをおススメします。
参考ページ
絵を描く感性を高める方法
学ぶことが困難と思われるのが、いかに感性を育てるのか⁉というところだと思います。
感性だけは学校で学ぶことは難しいと思います。
絵画教室でも、学べるところと学べないところがまちまちなので、絵画教室はしっかり調べる必要があります。
ここでは、独自に感性を育てる簡単な方法を紹介します。
その方法は何らかの動画を見て、自分なりに色や形を感じながら、その意識に従ってパステルや水彩などで絵を描いていきます。
基底材はB3画用紙くらいの大きさで、時間は数分から十数分程度で瞬間的に完成させていきます。
動画でなくても、人物や動物、植物を見ながら、自分の感じた色や形を描いていくのもよいでしょう。
これらの絵画は短時間で多く描かれるので、自分の絵画の特徴が分かるようになります。
描かれた絵画から、よいと思われるところや悪いと思われるところを発見して、絵画をブラッシュアップさせていってください。
特に意識したい要素は、描かれた絵から感じられる構図と、使用されている色彩の組み合わせ、そして、描写された線と形から感じられる動勢やマッス、ボリュームです。
これらは緻密に計算することなく、瞬間の判断で絵画の要素が構成されますが、何枚も描いて検証を重ねることで、絵画の要素は瞬時の判断でコントロールすることができるようになります。
このようなやり方は感性を高める一つの手法なので、自分なりに自由に改良して実践していきましょう。
参考ページ
2023年2月22日執筆公開